チューニングカーの 市民権とその未来
VOL.313 / 314
鈴木 高之 SUZUKI Takayuki
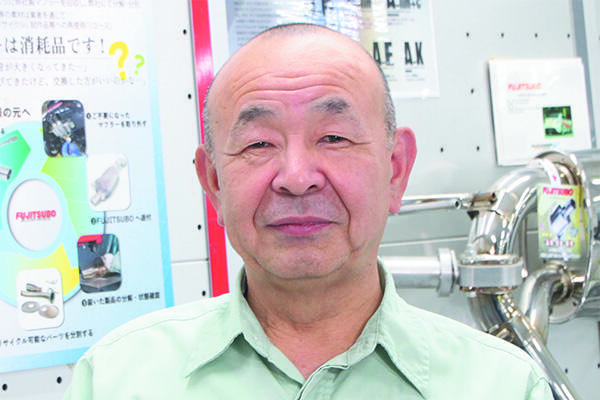
藤壺技研工業株式会社 常務取締役、NAPAC 副会長(元JASMA 事業部長)
1965年生まれ、東京都出身。神奈川県の高校を卒業後、自動車部品の卸売業者に就職。1991年より藤壺技研工業に入社し、JASMAの認知活動など自動車チューニング業界の社会的地位向上に尽力。2023年NAPAC副会長、JASMA事業部長などを歴任、現在に至る。
HUMAN TALK Vol.313(エンケイニュース2025年1月号に掲載)
1989年のJASMA(日本自動車スポーツマフラー協会)設立は当時「違法改造」「暴走族」といった社会的にネガティブなイメージだったチューニング業界に一石を投じる出来事でした。その立役者となったのがFUJITSUBOブランドで知られるエキゾーストパーツ業界の雄、藤壺技研工業株式会社。現在JASMA事業部長を務める鈴木高之氏にこれまでの経歴やこれからの業界の話などをうかがった。
チューニングカーの 市民権とその未来---[その1]

20歳で買った2台目の愛車はST165型セリカ
彼女は社長のお孫さん
東京で生まれ、5歳から横浜へと引っ越した鈴木氏。地元の高校を卒業後、車が好きだったことから自動車部品卸売業のトヨタ部品共販(当時)へと就職する。「会社自体はディーラーから部品の注文を受けて注文、配達するといういわゆる部品卸業です。私はそこで商品管理という物流を司る部門に勤めていました。最初に買った車は中古のA60型セリカでしたね。そして20歳になる頃、同期で入社した女性とお付き合いを始めまして、それが当時の藤壺技研工業の社長のお孫さん(現在の奥様)だったんです。時は1985年、フジツボのことは『マフラーを作っている会社』くらいの認識でした。改造車に対する法律は厳しく、少しでも車高を下げれば違法改造で警察に止められるような時代でした」そんなチューニング業界に対する風当たりが強かった1980年台中盤、鈴木氏は奥様との結婚を機に藤壺技研工業へ転職することを決意する。

初めて買った車はA60型セリカ

トヨタ共販時代
車検対応マフラーの誕生
鈴木氏が25歳で藤壺技研工業へと転職したのは1991年(平成3年)のこと。一方でJASMAが設立されたのは遡ること2年前の1989年。当時のチューニング業界は暴走族の社会的な問題が大手メディアでも取り上げられ、マフラーの出荷量も半減したという。「このままでは立ち行かないということで、当時のマフラー業界の代表の方々が団結して運輸省や警視庁へと働きかけていったそうです。とにかくバラバラに話をしても聞く耳を持ってくれないので、団体になって陳情しましょうと。それでできたのがJASMA(日本自動車スポーツマフラー協会)です。それまでは交換用マフラーの騒音基準は存在せず、あるのは新車の騒音基準だけ。車検時にチェックされるのはマフラーに穴が空いていないか、空ぶかしで爆音が出ないかどうかを見るだけで、マフラーを交換していいとか悪いとかを規制する法律は全く無かったんです。マフラーを交換することはあり得ないという前提ですね。そこでJASMAは騒音規制の内規を定め、それを守るのでマフラーの交換はダメと一律的に言うのは止めてくださいと働きかけました。そしてフジツボをはじめ、トラストさん、HKSさんなど各社それぞれのマフラーについて諸元表を全て自分達で作り、運輸省や全国の陸運事務局に送ったんです。『このマフラーはこの車に装着した時にこのような騒音値になり、こういう形でサイレンサーが2個付いています』というような全商品と適合する車種に関する書類を揃えて全国の陸事に送り、それで〝車検対応マフラー〟というのが認められたのです。とはいえ、判断は各陸事の担当者に委ねられるため、『車検対応マフラー?そんなもの知らん』と突っぱねられることもしばしばあったそうです」
ドアミラーを変えただけで車検に通らないような時代に、車検対応マフラーを認めてもらうため、アフターパーツメーカーの陰日向の努力がそこにはあったのです。
裾野工場開設と ISO9001認証取得
1991年頃は日産R-32GT-Rやシルビア、トヨタスープラなど華やかなスポーツカーが百花繚乱に市場を彩っていた時代でした。先達の努力の甲斐もあり、規制緩和が進んだチューニング市場ではダウンサスが認められるなど、社会的な認知も広がってきていました。「当時はタイヤの扁平率を変えたら車検に通らなかったのが、1994年〜95年くらいから外周が変わらなければOKとなり、ワイドタイヤが履けるようになった。ワイドタイヤ、アルミホイール、ダウンサスで車のスタイリングと走行性能は大きく変わりました。アフターパーツメーカーも各社本当に業績が伸びた頃だと思います。当社も1997年に裾野市に裾野総合工場を開設、ISO9001認証を取得するなど大きく変わっていきました。その背景には『アフターパーツを装着した特別仕様車は売れる』と自動車メーカー側が気付いたことが大きな要因としてあります。ディーラーオプションでマフラーやサスペンション、外装パーツなどを付けて販売するんです。オートサロンに自動車メーカーが出展し始めたのもこの2000年頃でした。その頃からディーラーオプションのパーツに当社のパーツが選ばれるようになった。製造側の品質管理もメーカー品質に適うものでなければならないため、裾野工場を新設し、ISOも取得したということです。アフターパーツのみの頃とは発注数量も桁違いですから、生産効率や品質の担保といった側面からもクォリティの向上は必須でした。当時はアフターパーツメーカーがISOを取得するなんて前例は無い中で、私が前職で色々な方針管理活動やQC活動の考え方を叩き込まれていたこともあって白羽の矢が立ったということです」

裾野工場設立時(後列右端が鈴木氏)
チューニングカーの 市民権とその未来---[その2]
HUMAN TALK Vol.314(エンケイニュース2025年2月号に掲載)
マフラーの部品認証化へ
1990年から2000年へとチューニングに対する規制緩和がどんどん進んだことにより、JASMAを脱退するマフラーメーカーが出始め、再び巷に爆音を轟かせるマフラーが増えてきました。その影響で2005年あたりから規制を厳しくするべきという話が持ち上がってきました。環境省の中央環境審議会の中の大気・騒音振動部会自動車単体騒音専門委員会にて走行騒音規制を見直し国際基準を導入することの検討が始まり、そこで交換用マフラーに今後騒音規制を掛けるべきか否かという議論が起こるという、業界を揺るがす一大転機が訪れたのです。
ちょうどその頃、私もJASMAの理事となり、技術委員や総務委員を担うことになりました。中央環境審議会専門家委員会の方も「どんなところでどのようにマフラーを作っているのか、マフラーメーカーの視察をしたい」ということで、弊社の方で視察の受け入れをし、理解を深めていただきました。それを機に「排除するのではなく、もっとちゃんとしていこう」という流れになり、話が部品認証化へと向かっていったのです。
今までは交換用マフラーの適、不適は車検で判断していた、あくまでも任意団体の自主規制でした。それを使用過程車への後付消音器(アフター用のマフラー)については、新たな試験方法で事前認証されていれば保安基準適合となり、2010年に「後付け消音器の事前認証制度」という新たな制度が誕生したのです。この制度に則って製造された交換用マフラーは保安基準に適合したマフラーとなったのです。

東京オートサロンでのJASMAブース
ISOとテストコース
事前認証制度に則ったマフラー作りをするためにはさまざまな条件がありました。まずテストをするための試験路が必要なので、静岡県裾野市の自社工場敷地内に走行騒音試験路を作りました。また品質マネジメント規格であるISO9001を持っていることも必須でしたが、幸いなことに弊社含めJASMA加盟の大半の企業は元々ISOを取得していたり、それに準じた品質を担保していたので、基準をクリアすることはそれほど大きな問題ではありませんでした。ただ制度をクリアするための試験内容が細かく、複雑になり、試験も国土交通省が定めた認証機関が行い、公正に判断しなければならないというのが大きな違いでした。しかし、全てのJASMA加盟企業が騒音試験路を保有しているわけではありません。そのような場合は弊社のテストコースを各企業に貸し出し、試験は認証機関が行います。弊社は公正な試験場を管理するため、試験機関認証のISO17025も取得しています。そのくらい厳格に定められた製造、そして品質マネジメントシステムのもとに作られたマフラーが公正なテストを経て得られる事前認証のお墨付きだからこそ、信頼して使っていただける。そのようなマフラー業界の発展に寄与するためのさまざまな活動を弊社として、常々行なってきました。

藤壺技研工業敷地内騒音試験センター
JASMAの使命、 FUJITSUBOの使命
2024年10月、JASMA事業部、ASEA事業部、JAWA事業部の3つの事業部がNAPACへと一本化されました。それぞれの事業部が担っていた役割や名称はそのまま残りつつ、さらなる組織強化と効率化が図られることとなったのです。そのJASMAとして一番取り組むべきことと思っているのは「普及活動」です。例えば中古でマフラーを買ったらJASMAのマフラーじゃなくて爆音マフラーだった、のようなことにならないよう、一般消費者の方がマフラー選びの際に指標となる旗印としてのJASMAです。一昔前のように捕まったら外せばいいではなく、周辺の住民含めて迷惑が掛からないようにスマートにカスタムを楽しむ。そのお墨付きがJASMAであり「JASMA基準で作った安心・安全なマフラーを選びましょう」という普及活動をしながら、国土交通省側には「私たちは今、合法的な手段できちんとマフラー作りをやっていますよ」というアピールをする。そのように使う側と規制する側の橋渡しをするのが我々の役目だと思っています。
もし全ての車がEV化してしまったらマフラーは不要なものになります。しかし、エンジン車は少なくなっても無くならないと思うんです。そのエンジン車を愛する人々に我々はどういうアプローチができるか。マフラーって稀有なパーツなんです。音も見た目も、そして機能もアップする、そんな五感に訴えるパーツってなかなか無い。今のエンジン車を大事に10年、20年と乗り続ける人がいる限り、いつかマフラーに穴が空き、交換パーツの供給を純正がやめてしまっても我々はそれを作り続けなければならない。それが我々の使命だと思っています。

東京オートサロンでのJASMAブース
